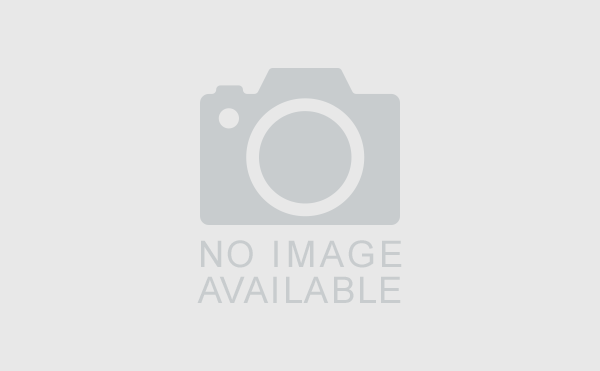2024年度 冬期博物館実習4日目(1月15日)
こんにちは。実習4日目のブログを担当します、追手門学院大学のN.Mです。
4日目では、私達の班は学芸員の横川さんにご指導頂き、植物標本についての実習を行いました。
まず、午前に植物標本の概要、収蔵過程などを解説頂いた後、植物標本製作室や特別収蔵庫を見学し、植物標本のラベル張り作業を通して様々な標本を鑑賞しました。
最初に見学した植物標本製作室では、採集した植物を乾燥させて台紙に貼り、標本するまでの流れについてなどを解説して頂いたのですが、乾燥のさせ方や台紙の素材、貼り付け方ひとつひとつに全て意味があり、資料を未来に繋げるために考えられた方法のだと学びました。例えば、植物を台紙に貼り付けるラミントンテープは熱を加えることではじめて粘着させることができる特性があります。この特性を利用し、台紙にだけ接着させて植物本体に粘着物質が付かないように保存して、必要あれば台紙からも比較的容易に取り外せるようになっており、植物標本が傷つかないことを第一に考えられているのだと学びました。また、標本によっては、フラグメントパケットと呼ばれる、種子や標本にする際に取れてしまった一部分など、様々な理由で一緒に保存したいものを入れたものが貼り付けられていることもここで学びました。これも標本そのものに傷をつけないための配慮であり、いかに当時の状態を保存し続けるか考え尽くされていると感じました。
特別収蔵庫見学、ラベル張り作業では、非常に多くの標本を鑑賞しました。後者では、大阪市立自然史博物館に寄贈された標本にどこから寄贈されたのかが分かるよう、一枚一枚に補足説明がされたラベルを貼り付ける作業を通して鑑賞したのですが、植物だけでなく、保存ラベルにも多種多様さがあることが分かりました。保存した経緯が詳しく記載されているものや、地図が貼り付けられているもの、採集前の写真が同封されているものなど、ラベルに必要な情報が記載されつつも採集者の個性が現れている標本を鑑賞することができ、標本から得られる情報の幅広さに驚きました。
もちろん、植物標本そのものの多種多様さにも驚かされました。同じ植物の標本であっても、採集する季節の違いや、発芽途中といった状態の違いなど、様々な状態が保存されており、求められる資料の多さ、多様さを学びました。また、約A3サイズの台紙に収める必要から、茎が折られたものや、大きい葉だけのものもあり、鑑賞していてとても興味深かったです。
午後ではラベル張り作業後に採集者から依頼された標本の同定調査を行いました。
ヒルムシロらしき標本の同定作業を行ったのですが、ヒルムシロという水生植物は通常、3~4cmの大きさの葉をつけます。調査対象の標本は、他の部分はヒルムシロの特徴と一致しているにも関わらず、1~2cmの葉しかないため、同定が依頼されたとのことでした。収蔵庫内のヒルムシロの標本と見比べ、同じような状態の標本が無いか調べることで同定を行ったのですが、確かにほとんどが3~4cmの葉をつけていました。私は今回の調査で初めてヒルムシロという植物を知ったのですが、沢山の標本と見比べることで、植物に詳しくないながらもその歪さを感じることができました。
一方で、調査を進めると、体感になりますが、大体30~40:1の比率で1~2cmの葉をつけたヒルムシロと同定されている標本を確認することもできました。そしてここから、調査対象の標本も同じようにヒルムシロだと同定できるのではないかと推測することができました。この推測は同じ植物の標本が複数収集され、保存されていたからこそできたことです。この調査を通して、私は身をもって資料収集と資料保存の大切さを学びました。
見学・作業・調査を通して、非常に様々な標本を鑑賞しましたが、同じ植物標本でも個体差があり、発芽直後や、成長途中といった状態が異なるものも沢山保存されているといった初歩的な学びはもちろん、資料収集や資料保存の大切さといった、博物館の存在意義を再確認した学びなど、非常に多くの学びを得ることができました。