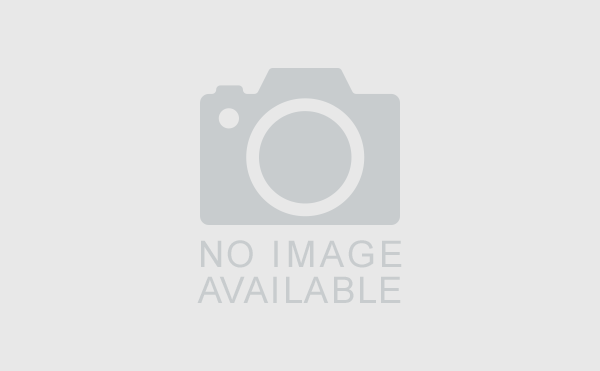2024年度 冬季博物館実習4日目 (1月15日)
こんにちは!近畿大学のH.I.です。
実習4日目の1月15日、私たちの班は学芸員の中条さんのご指導のもと、主に収蔵庫で砂の標本の整理作業を行いました。
初めは、「なぜ砂の標本を集めているのだろう?」と疑問に思いました。その際、中条さんから、砂が枯渇しつつある貴重な天然資源であることを教えていただきました。砂はなんと水に次いで多く使われている資源であり、コンクリートや埋立地の材料、さらにパソコンやガラスを作るためにも欠かせない素材です。しかし、砂は自然界で長い時間をかけて作られるものであり、その供給には限りがあります。
世界的には砂の枯渇が進んでおり、ある国では砂をめぐる争いが激化し、マフィアによる収奪や虐殺が行われた事例もあるそうです。また、海などの砂を過剰に利用すると、生物の多様性が失われ、景観も悪化します。
こうした背景から、この博物館では日本各地の砂を2010年頃から積極的に収集し、地域別に整理して保管されているそうです。
砂の標本には1つ1つに標本番号が振り分けられ、その標本番号が合っているのか確認し、決まったところに配架しました。この砂の整理作業は、体力を使う地道な作業で、間違えないように緊張もしました。標本を収集し保管すること自体にとても手間がかかることを知り、その大変さを実感しました。作業中に砂を見てみると、地域ごとに砂の細かさや色、形が異なり、とても興味深かったです。これからは、海などで砂の上を歩くときに、砂の特徴をじっくり観察してみようと思います。
午後は砂の標本の整理作業に加えて、博物館のプレハブの片付け作業にも参加しました。プレハブの中には、これまで博物館で使用された看板や、昔に集められたボーリングコア、お米の脱穀に使う千歯こぎ、そして日本ではあまり見かけない大きな植物などがあり、見ているだけでワクワクするようなものがたくさんありました。
片付け作業では、看板の重しとして使われている土のうの整理を行いましたが、これが重くてとても大変でした。博物館は収蔵されている資料以外にも多くのものがあり、その管理や整理の大変さを改めて感じました。