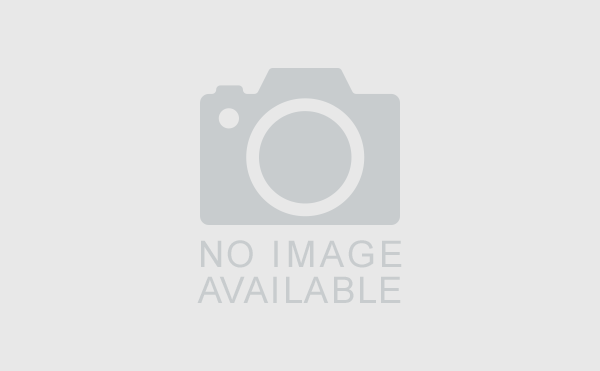2024年度 冬季博物館実習1日目(1月11日)
初日の実習生ブログを担当します、大阪大学のY.Mです。よろしくお願いします。
初日の実習はオリエンテーションからスタートしました。配布された博物館実習資料を使用し、大阪市立自然史博物館について学びました。博物館施設の概要や、博物館の沿革について学ぶことができました。
次に、博物館の展示室を実際に見学しました。展示について、特に展示物のメンテナンスの観点に焦点を当て、解説いただきました。展示を作る際、博物館の設計段階からメンテナンスのしやすさ、掃除のしやすさを見通した展示づくりをする必要があることを理解することができました。
私は大学で文学部に所属しており、人文科学(その中でも芸術関連)を学んでいます。所属大学の学芸員課程は文学部で開講されていることから、美術品や歴史資料を扱うことを想定された授業が多いです。私自身、大学で人文科学を学びながらも自然科学に興味があったため、大阪市立自然史博物館で実習することを決めたのですが、展示物や展示方法など大学の授業で学んだことと少し異なる視点を感じることができ、非常に興味深かったです。特に美術品では基本的に、その展示物(美術品)のみをどのように展示するかを考えます。しかし、例えば動物の標本では標本のみを展示するのではなく、その動物が生きている環境や周囲に存在する植物や動物までを含めて考えられた展示があることを知りました。
午後からは、実習2日目、3日目に行われる博物館のイベントである「はくぶつかん・たんけん隊」についての研修がありました。「はくぶつかん・たんけん隊」は、子どもたちが博物館の普段は見られない場所(収蔵庫などのバックヤード)を探検するというものです。研修では、イベントの概要、実施要項についての説明を受けた後、実際のツアー順路を歩き、見学しました。一般収蔵庫、特別収蔵庫、液浸収蔵庫のそれぞれの収蔵庫には圧倒される数の標本が保管されていました。貴重な資料が数多くあり、大人も子どももワクワクしてしまう場所だと感じました。
諸説ありますが、博物館の前身とされるWunderkammer(驚異の部屋)はなんでも珍しい物を集めていたことからそう名付けられたそうです。実際に収蔵庫に足を踏み入れてみると、普段の生活ではなかなか目にしないものがたくさんあり、圧倒されるとともにWunderkammerと呼ばれた理由に心から納得しました。様々なものを集め、整理し、保管するという博物館の役割の重要性を改めて感じました。