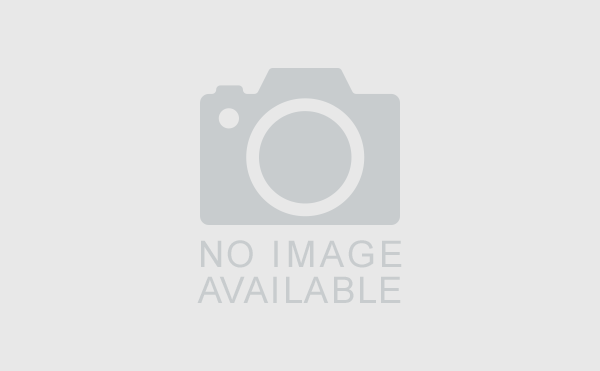2024年度 冬季博物館実習 2日目 (1月12日)
こんにちは。実習2日目を担当します、近畿大学のU.Rです。
2日目では学芸員の和田さんの指導の下、ヤギの骨を洗う作業を行いました。骨を洗う作業の前に30分程度骨格標本になるまでの過程や、資料の受け入れ方、記録の付け方の簡単なレクチャーがありました。骨格標本になるまでの過程については、小さい骨は水につけて腐らせ、大きい骨は砂場に置くなど処理の方法にはそれぞれ違いがあります。資料の受け入れについては、資料の大半は寄贈及び交換で成り立っており、そのまま博物館に持ってくる人や、郵送で送られてくる場合など様々ですが、共通していえることは、産地と収集日がないと引き取ることができないということです。寄贈者と採集者は違う場合もあるので記録をつける際は注意しなければならないということも知りました。このように、博物館資料はとにかく記録を正確に長く残すということが重要であると学びました。
その後、午前・午後を通して実際に骨を洗う作業を行いました。私が洗ったのは前足の部分でした。もちろん骨を洗う経験などこれまでなく、医療用のメスや、歯医者で使用される鎌状の器具など普段目にすることのない道具を使うこともあり、手先が器用ではない私には少し難易度が高かったです。金属の器具で無理に筋や肉を取ろうとすると、骨に傷が入ってしまう恐れがあるため、かなり慎重に作業を行いました。その結果、前足の一部分でさえ、実習中に終わらせることが出来ませんでした。骨を洗う作業は標本になるまでののほんの一部分に過ぎず、ここから組み立てる作業などもあるらしく、1つの骨格標本が完成するまで相当な時間がかかるのだと身をもって感じました。しかし和田さんによると、頭骨の状態で判断して回収するらしく、私が実際に洗った骨は、結果的にもう少し腐らせると楽に作業できたと実習後に知り、少し安心した自分もいました。
2日目はずっと骨を洗う作業でしたが、学芸員の大変さを知ることができたことに加えて、普段できない貴重な経験をすることができ、とても新鮮で楽しい実習になりました。