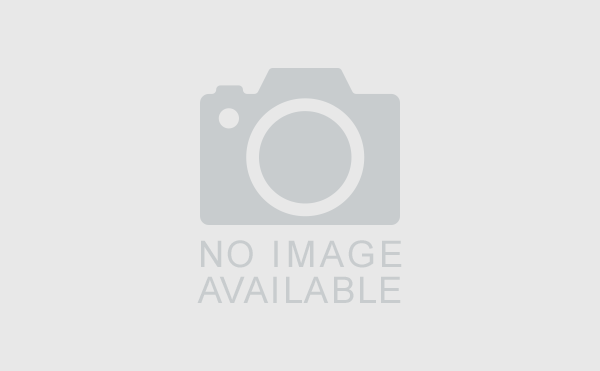2024年度 冬季博物館実習 4日目(1月15日)
こんにちは。実習4日目のブログを担当する神戸大学のK.Kです。
4日目は植物研究室の学芸員の方の担当の元、菌類(サルノコシカケなど)の標本の確認と整理を行いました。この標本は別の博物館に収蔵されていたものだったのですが、その博物館で収蔵できなくなり廃棄されるところだったため、大阪市立自然史博物館に持ち込まれたものと聞きました。
はじめに、標本を収蔵庫から作業を行う実習室に運びました。収蔵庫から実習室へは段差がないように設計されているため、安全かつスムーズに資料を運ぶことができます。
今回の確認と整理作業では標本にはリストが付属していたため、リスト通りに標本が存在するかということとを確認したうえで、記載と異なる場合はリストに補足を記入しました。確認時は標本の種名を五十音順でソートし、その順番で段ボール箱に入れなおしました。サルノコシカケとテングタケのなかまに限って標本の整理を行いましたが、500点以上存在したため確認作業は4人がかりで3時間以上かかりました。
作業を行った標本は他の博物館の学芸員の方が扱っていたこともあり、密閉されたうえでケース内に名称や産地、採取者名などが記載されていました。そのため、確認作業は基本的に単純で、標本ケース内の記載とリストの記載に違いが無いかをチェックするだけで済みました。しかし、アマチュアの方が寄託された標本や資料ではリストがまとめられていない場合やリストと資料が正確でない場合などがあり、そのときは膨大な作業量になるとのことです。
この整理作業を通して、学芸員業務の多様さと追いついていない仕事の量の多さを実感しました。今でも収蔵庫には数十年前から開けられていない箱や未整理の資料が存在するとのことで、リストに記載されておらず「再発見」される資料もあるそうです。一方で、収蔵庫の容量は限界に近づいており、博物館のおかれている現状が厳しいものであることも改めて認識することができました。