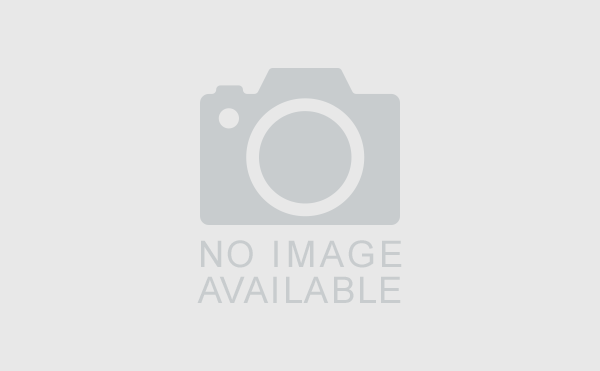博物館実習(2024年度 冬期)1月16日
1月16日実習分を担当する神戸大学T.Wです。
この日は、植物研究室の学芸員である長谷川さんの指導の下、ラベルの登録が完了している植物標本を学名順に整理する作業を行いました。この作業を完了することで収蔵棚に収める事ができます。ラベル登録を行った標本を収蔵棚に整理することは
- 標本を適切に保管できるようになる
- 公開されている標本を外部の人間が実際に閲覧できるようになる
という2つの意義を持ちます。1は主に収集・保管の観点で、2は研究利用や教育普及の観点でそれぞれ重要になるものです。
標本の中には、採集日や採集場所や、和名は記載されているが、学名が記載されていないものがありました。それらの標本は、植物辞典で学名を調べて付箋に学名を記して次に見る人が分かるようにしました。
ところで、ラベル登録されている標本は、外部に標本の存在が公開されている標本です。つまり、その標本を閲覧したいという研究者が現れる可能性があります。しかし今回のようにラベル登録された標本が段ボールに入れられて山積みになっていると、その中から見たい標本を取ってくることは非常に困難です。ですから標本整理は、単純な作業ではありますが博物館にとっては非常に重要な仕事です。今回整理した標本の中には60年以上前に収集された標本も多くありました。これらが収蔵庫に収められることで初めて研究者が使える博物館資料になるのです。長谷川さんが「とても気の長い話でしょう。」と仰っていたことが印象に残っています。
最後に私が今回の作業で疑問に感じた事を述べて終わります。それは収蔵庫の防災対策についてです。収蔵庫内には高く積みあがった段ボールが多くありました。その中には貴重な標本が多く保管されているにもかかわらず、地震災害時の転倒防止策がとられていないように見受けられました。近年南海トラフ地震の危険性が高まっていると指摘されているなかで、標本を整理するスペースが無いため、物が天井付近まで積みあがっているという状況は速やかに改善すべきです。そのためには公立博物館である以上行政が必要な対策を講じなければならないと考えられます。