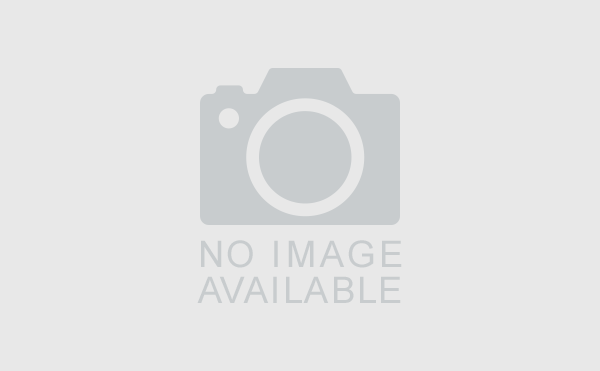菌類学講座「アマチュアでも出来る! アセタケ沼の楽しみ方」
2010年以降、博物館では毎年1月の自然史オープンセミナーを菌類学講座をするようにしています。これは前年開催したきのこの特別展でのセミナーをやったことで、担当の佐久間学芸員が外の人も呼んでいろんなきのこの話題を自分も勉強する機会にしたい、そして自分も年のはじめは初心に戻ってきのこのことをやりたい、ということでこの形になっています。幸いにも関西菌類談話会の共催ももらって、キノコ好きの人たちが集まる機会になっています。
さて、今年はきのこの中でもあまり知られていない、でもある筋では有名な「アセタケ」を取り上げます。
アセタケ・・漢字では汗茸、となるでしょうか。辛いわけではありません。実は毒キノコでして、代謝がおかしくなって、冷や汗を書くという洒落にならないきのこです。なので、このきのこに詳しくなっても食べられるきのこの知識にはちっとも繋がらないというグループです。
でも、そんなきのこを、仕事でもないのに、本気で取り組んでいるのが大西誠司さんです。標本をどんなふうに観察してるのか、顕微鏡で計測も含めて取り組んでいるやり方、そして、DNAにまで挑戦するその状況をお話しいただきました。
その中で博物館にこれをやってほしい、などの要求もいただきました。今後の取組の参考にしっかりさせていただきたいと思います。
当日は本郷次雄氏の描いた図鑑原図を見ながら、皆できのこ談義をする姿も。オンラインで聞けるようになり便利な講演会ですが、現場に行くと違った刺激を得られる部分もあるでしょう。3月以降には特別展「貝に沼る」関連の講演会も開催されます。現地で、またオンラインでお楽しみください。
大西さんの講演は2月18日まで、見逃し配信でご覧いただけます。これも便利な仕掛けですね。