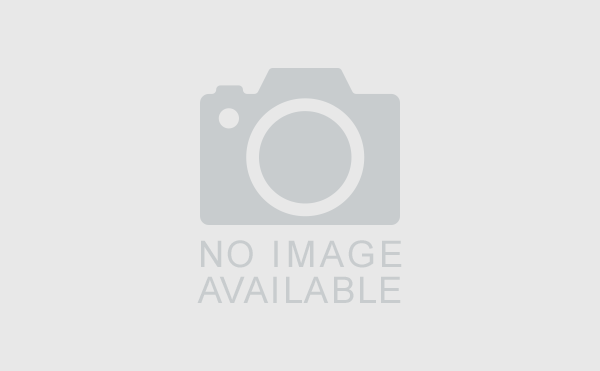2024年度冬季博物館実習4日目
滋賀県立大学のM.Tです。
博物館実習4日目は、松本学芸員のご指導のもと、昆虫標本の作製を行いました。
午前中は昆虫資料の収集方法や収蔵状況などの説明を受けた後、様々な昆虫標本を収蔵している特別収蔵庫を見学しました。昆虫資料は標本の寄贈や昆虫の捕集によって収集され、保存できる状態にした後、資料として登録されますが、登録するまでの作業が追いつかず、まだ資料として登録されていない標本が何千点もあるということを聞きました。また登録済みの標本に関しても、収蔵庫のスペース不足や、グループ毎に分けて収蔵する作業の人手など、収蔵するまでにも様々な課題があり、資金との兼ね合いとも合わせて解決が難しい課題であると感じました。
また、午前中は脱脂綿に置いて乾燥させていた昆虫を台紙に貼り付け、ラベルを付ける作業も行いました。チョウやカブトムシなどのサイズの大きい昆虫では体に針を刺し、展翅板を用いて乾燥させて標本にしますが、比較的小さい昆虫の標本を作製する際は、脱脂綿にのせて乾燥させた上で、台紙に貼り付けて標本にするということを聞きました。昆虫を観察する時はどうしても昆虫の羽や模様、色などの目立つ特徴に注目しがちですが、形態同定をする上では脚の付け根や腹側の形など、目立たない箇所が重要となることもあり、裏側が見えるようにすることが重要だそうです。そのため、貼り付ける台紙も三角形に切ったものを用い、角の部分に昆虫を貼り付けるようにしていました。このように、標本を作製する上での細かな作業や工夫にも意味があり、標本作製の上で重要であると感じました。
午後は午前中に作製した昆虫標本の形態同定を何種か行った後、午前と同様の標本作製作業を行いました。同定したものの一つにクロウリハムシがありました。クロウリハムシかどうかを見分ける際、脚や腹側を見る必要があり、改めて三角形の台紙に貼り付ける必要性を感じました。他の昆虫を同定する際も、細かなところまで観察する必要があり難しいと思いました。また、例えばテントウムシに似せている別の種がいるように、一見すると同種に見えるものも実は全く異なるグループに所属していたり、色や形が異なる種に見えても実は同種であったりなど、種内や種間にも多様性があり面白いと思いました。
昆虫標本に関して収集方法、作製方法、保管方法やそれに関する様々な課題を知ることが出来ました。今回行った標本作成作業は資料が収蔵されるまでのほんの一部分ですが、他にも様々な過程を経て、資料は展示や研究などに活用されていることを実感しました。