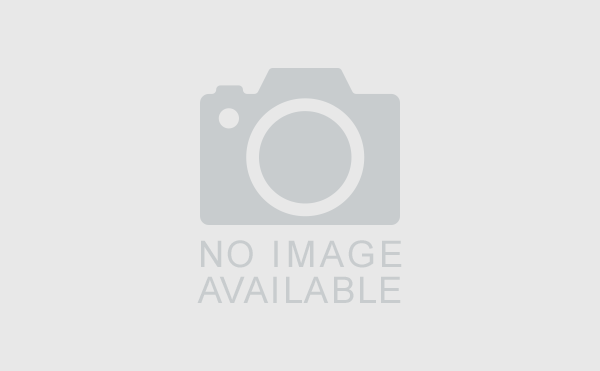2024年度 冬季博物館実習 5日目(1月16日)
こんにちは。奈良女子大学のI.Mです。
実習最終日となる5日目は館長の川端さんのご指導のもと、大阪の河原で採取された石を標本に登録するためのデータ入力作業、寄贈物の仕分け、特別展展示室内の清掃作業を行いました。データ入力は主に淀川水系の木津川、猪名川で採取された石を対象に行いました。川の上流付近の石も流れてくるため、河原には様々な種類の石が集まるそうです。最初は石の種類を全く判別できませんでしたが、石の図鑑を見たり、解説を聞いたりするうちに色や質感、模様などでそれぞれの石の特徴を少しずつ理解できるようになりました。また、石の見分け方はそのような形態的特徴から見分けるほかにx線をあてて石の成分を推測する方法もあり、より正確に同定することができると知りました。
その後、川端さんから大阪府全域の自然を展示している「大阪の自然誌」の部屋案内をしていただきました。展示物には鉱物も展示されており、研磨という石を削ったり切断したりすることで表面を綺麗に見せる工程を経た石の展示もされていました。研磨されている石とされていない石の違いは一例として、前者が石に興味を持ってもらうため、後者が視覚に障がいを持っている方でも表面の質感で種類ごとに見分けやすいようにするためであると聞き、来館者に向けて様々な配慮がされているのだとわかりました。
午後は博物館に個人で寄贈された収集品の仕分けを行いました。博物館では個人で寄贈された資料を引き取り、学芸員による鑑定をおこなった後、標本として登録するかどうかを決めています。そのため、各専門分野の学芸員が化石を鑑定できるようにするために、仕分けでは分類が書かれたデータをもとに化石を4種類に分別する作業を行いました。仕分けでは資料を運ぶ回数が多いため、学芸員の仕事は体力勝負でもあると思いました。仕分けが終わったあとは令和7年2月22日(土)から5月6日(火)まで開催される特別展「貝に沼る-日本の貝類学研究300年史-」の展示室内に設置される展示ケースの清掃を行いました。展示開催期間中はケース内部の清掃ができないため、入念に清掃を行う必要があるそうです。
この日は資料がどのような過程を経て標本に登録されているのか学べただけでなく、博物館が来館者に来てもらえるようにするために展示方法にどのような配慮を行なっているのか具体的に知ることができました。