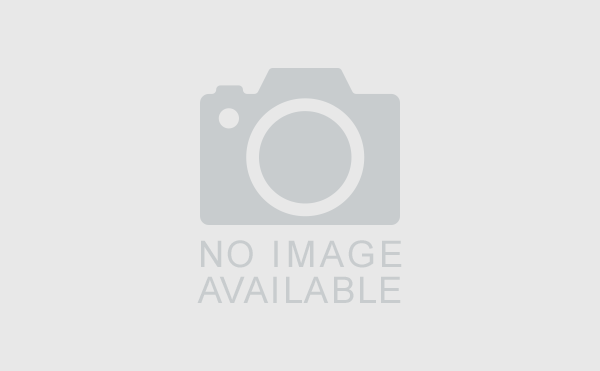2024年度 冬季博物館実習 4日目(1月15日)
こんちは。実習4日目のブログを担当します、岐阜大学のS.Kです。
実習4日目、私達の班は第四紀研究室の石井学芸員のご指導のもと、ボーリング資料に関する実習を行いました。
午前中はまず、収蔵庫でボーリング資料について説明していただきました。ボーリング調査とは地盤を筒状にくり抜き、掘り出した地層を分析することで地質や地盤の状態を調べる調査です。この調査によって得られた資料をボーリング資料といい、大阪市立自然史博物館には研究や工事のために行った調査の標本資料がたくさん保管されています。収集した標本をもとに柱状図を作成し、それを比較することで実際には観察することのできない地層の様子を推測することができるという役割があると学びました。その後、一般展示を見学し、柱状図から実際にどのようなことが分かったのかを説明していただきました。標本によって過去の大阪市の地形の変化の様子、活断層の動き、噴火の様子など様々なことが分かると教えていただきました。
ボーリング資料の重要性について学んだ後は、午後にかけて、柱状図のデータ入力を行いました。調査の基本情報から、調査によって分かった土質区分・色調・密度やその他の詳細データをデジタルファイルに入力しました。
紙の資料として保管されている柱状図データをデジタル化し、他の研究機関、公的機関とシェア可能な形式にすることが目的であると教えていただきました。データ入力はかなりの量があり、詳細な所見などを全て手作業で入力するのはとても労力が必要であると感じましたが、調査会社によっては調査結果入力に使用しているソフトが異なっていたりするため、最初からデジタルデータとして受け入れをするということは難しいとのことでした。長期保存の面からは紙媒体の方が優れていますが、データ資料の方が場所を取らず管理がしやすいという点と上手く折り合いを付けなければいけない博物館側の苦労を感じました。
この日はボーリング資料からは実際の地質や地層の様子だけでなく、過去の地形やその変化の様子など様々なことが読み取れることを学びました。また、特に採取した資料を全て保管するオールコアボーリング資料は、収蔵庫内で場所を取っていたため、多くの現物資料を保管しなければならない博物館としての目的と、実際の物理的限界にギャップがある点が課題であると感じました。