ミニ展示「植物の標本を使って研究する」 令和7年5月:日本のシマオオタニワタリ類の分類学的研究とその関連標本を紹介します
大阪市立自然史博物館では、所蔵する植物標本を使った研究を月替わりで紹介するミニ展示を開催中です。本展示は、令和6年6月1日(土)から令和7年6月1日(日)まで、本館1階ナウマンホールにてご覧いただけます。最終回である第12回となる令和7年5月の展示では、瀬戸(1979)による日本のシマオオタニワタリ類に関する論考とMurakami et al. (1999) によるDNA分析に基づくヤエヤマオオタニワタリの新種記載に関する研究を紹介します。
大きな葉を持つ着生シダであるシマオオタニワタリ類は、日本に3 種知られています。これらは互いによく似ており、形態による識別は難しいとされています。大阪市立自然史博物館の学芸員だった瀬戸剛さんは、日本のシマオオタニワタリ類を紹介する論考の中で、分類学的な取り扱いが混乱していた琉球南部のシマオオタニワタリ類について、葉が水平に出てから斜上するという形質などを重視し、未記載種(和名:ヤエヤマオオタニワタリ)である可能性を指摘しました。のちに京都大学(当時)の村上哲明さんたちによるDNA 分析によって、瀬戸剛さんの指摘が実証され、ヤエヤマオオタニワタリは新種Asplenium setoi N.Murak. et Seriz.として記載されました。学名の中の「setoi」は、形態から未記載種である可能性を指摘していた瀬戸剛さんに対する献名です。
瀬戸剛さんの論考では標本は引用されていませんが、博物館が所蔵するシマオオタニワタリ類の標本を見ると、瀬戸剛さんによる注釈ラベルが付けられており、論考を執筆する際にそれらの標本を検討していた様子がうかがえます。
令和7年4 月22 日、瀬戸剛さんは95 歳で逝去されました。瀬戸剛さんは大阪市立自然史博物館の植物担当学芸員として、シダ植物の研究と標本室の充実と発展に尽力されてきました。これまでの功績を称え、月替わりのミニ展示「植物の標本を使って研究する」の最終回で、その研究成果と関連標本を紹介させていただきます。
5月に紹介する研究:
瀬戸剛 1979. 日本のオオタニワタリとその類品.南紀生物 21(1): 6-9.
Murakami N., Watanabe M, Yokoyama J., Yatabe Y., Iwasaki H., Serizawa S. 1999. Molecular Taxonomic Study and Revision of the Three Japanese Species of Asplenium sect. Thamnopteris. Journal of Plant Research 112:15-25.
ミニ展示の概要については過去のWhat‘s new『ミニ展示「植物の標本を使って研究する」を開催します』(https://omnh.jp/archives/11362)をご覧ください。
※なるべく月替わりで展示を入れ替えますが、担当者の都合で入れ替えが数日前後することがあります。ご了承ください。

令和7年5月の展示:日本のシマオオタニワタリ類の分類学的研究とその関連標本の展示。研究で検討された標本と論文を展示します。1年にわたる12回の展示のグランドフィナーレということで、展示ケースを1つ増設しました。
本展示に関する問合せ:植物研究室・横川

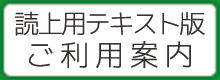
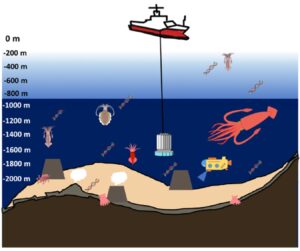
-300x225.jpg)